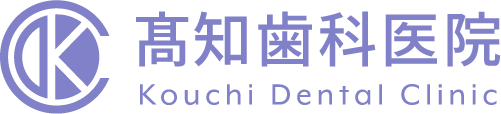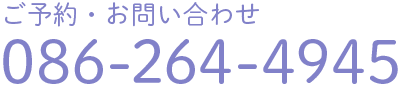2025.08.28
【口臭が気になる方へ】原因と対策を歯科医が徹底解説
こんにちは。岡山市南区福浜町の髙知歯科医院、院長の髙知信介です。
「人と話すときに口臭が気になる」「家族から指摘された」など、口臭は誰もが一度は悩む可能性のある身近な問題です。
しかし、実際には口臭の多くがお口の中の環境に原因があることをご存じでしょうか。この記事では、歯科医師の立場から口臭の原因とその正しい対策について、徹底的に解説いたします。
目次
-
口臭とは何か? ― 生理的口臭と病的口臭
-
口臭の主な原因
2-1. 舌苔(ぜったい)
2-2. 歯周病
2-3. むし歯・詰め物の不良
2-4. 口腔乾燥(ドライマウス)
2-5. 全身疾患による口臭 -
口臭を悪化させる生活習慣
-
自分でできる口臭対策
4-1. 正しい歯磨きとフロス・歯間ブラシの活用
4-2. 舌清掃の習慣化
4-3. 唾液分泌を促す工夫
4-4. 食生活の改善 -
歯科医院でできる口臭治療
5-1. 歯周病治療
5-2. プロフェッショナルクリーニング
5-3. ドライマウスへの対応 -
口臭に関するよくある誤解
-
まとめ ― 口臭は正しい理解とケアで改善できる
1. 口臭とは何か? ― 生理的口臭と病的口臭
口臭には大きく分けて生理的口臭と病的口臭があります。
-
生理的口臭
朝起きたときや空腹時に一時的に強くなる口臭。これは唾液の分泌が減ることで起こります。誰にでも生じる自然な現象であり、歯磨きや飲食で軽減します。 -
病的口臭
歯周病や舌苔、むし歯、全身疾患など、何らかの病気や異常が原因で起こる口臭。適切な治療を行わなければ改善しません。
口臭でお悩みの方の多くは、この病的口臭に該当します。
2. 口臭の主な原因
2-1. 舌苔(ぜったい)
舌の表面に白っぽく付着する細菌の塊を「舌苔」と呼びます。
揮発性硫黄化合物(VSC)を産生する細菌が多く存在しており、口臭の最大の原因のひとつです。
2-2. 歯周病
歯ぐきの炎症や歯周ポケット内に細菌が増えることで、強い口臭が発生します。
進行した歯周病では、歯ぐきから膿が出ることもあり、特有の不快な臭いを伴います。
2-3. むし歯・詰め物の不良
むし歯の穴や古い詰め物の隙間に食べかすが溜まり、細菌が繁殖すると口臭の原因になります。
2-4. 口腔乾燥(ドライマウス)
唾液には細菌を洗い流す作用があります。唾液の分泌が減少すると細菌が増え、口臭が強くなります。加齢、薬の副作用、ストレスなどが原因となります。
2-5. 全身疾患による口臭
糖尿病、肝疾患、腎不全、胃腸疾患など、全身の病気が原因で口臭が出る場合もあります。この場合は医科との連携が必要です。
3. 口臭を悪化させる生活習慣
-
喫煙
-
強い臭いの食べ物(にんにく・ニラ・アルコール)
-
水分不足
-
ストレスや不規則な生活
これらは口臭を一時的または慢性的に悪化させます。
4. 自分でできる口臭対策
4-1. 正しい歯磨きとフロス・歯間ブラシの活用
歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは落とせません。
デンタルフロスや歯間ブラシを毎日使用することが、口臭予防に効果的です。
4-2. 舌清掃の習慣化
舌ブラシを使って軽く舌を清掃しましょう。強く擦ると粘膜を傷つけるため、やさしく行うことが大切です。
4-3. 唾液分泌を促す工夫
よく噛んで食べる、ガムを噛む、水分をしっかり摂ることが効果的です。
4-4. 食生活の改善
バランスのとれた食事、発酵食品や食物繊維を含む食品を取り入れることで、腸内環境の改善が口臭軽減につながることもあります。
5. 歯科医院でできる口臭治療
5-1. 歯周病治療
スケーリングやルートプレーニングで歯石を除去し、歯ぐきの炎症を改善します。
5-2. プロフェッショナルクリーニング
定期的に歯科衛生士によるクリーニングを受けることで、普段の歯磨きでは落とせない汚れを除去できます。
5-3. ドライマウスへの対応
保湿ジェルや口腔機能検査、必要に応じて生活習慣指導や医科への紹介を行います。
6. 口臭に関するよくある誤解
-
「マウスウォッシュだけで解決できる」 → 一時的に臭いを抑える効果はありますが、根本的な解決にはなりません。
-
「歯磨きをたくさんすればいい」 → 強すぎるブラッシングは逆に歯ぐきを傷つけ、炎症や口臭の原因となります。
-
「口臭は自分で分かる」 → 実際には自分の口臭を正しく認識することは難しく、専門的な検査が必要です。
7. まとめ ― 口臭は正しい理解とケアで改善できる
口臭は「体質だから仕方ない」と思われがちですが、実際の多くは歯周病や舌苔など、お口の問題を解決することで改善可能です。
毎日のセルフケアに加え、歯科医院での定期的な検診・治療を受けることで、口臭の悩みは大きく軽減できます。
人と安心して会話できるように、ぜひ一度、歯科医院でのチェックをおすすめします。
執筆:髙知歯科医院 院長 髙知信介(日本歯周病学会認定医)